三柱山古墳
データ
| 名前 | 三柱山古墳 |
|---|---|
| よみがな | みはしらやまこふん |
| 形 | 円墳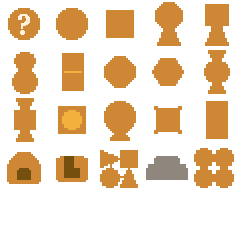 |
| 都道府県 | 大分 ( マップ | 一覧 ) |
| 所在地 | 大分県宇佐市安心院町下毛 |
| 駐車スペース | あり |
| 交通 - 徒歩 | -- |
| 交通 - 車 | -- |
| 周辺情報 | |
| タグ | -- |
| キーワード | 石棺, 弥生時代終末期, 三女神社, 遥拝所 |
| 注意事項 | -- |
| 紹介文 |
「安心院町宮ノ原遺跡」(安心院町教育委員会 1984年3月31日)記載の第8石棺群が発見されている(p.91)。 |
posted by katumoku10
updated 2025年07月30日
updated 2025年07月30日
投稿写真 (3)

| 
| 
|
- < 前へ
- 次へ >

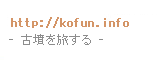
源次様
刮目天です。いろいろと貴重な情報をありがとうございました。早速、安心院町誌を調べて、以下のブログ記事にしました。
「【刮目天の古代史】三柱山古墳は卑弥呼の墓だよ!」
https://katumoku10.hatenablog.com/entry/2025/08/03/022030
現在までの結論は以下のとおりです。
①当方が主張する「三柱山古墳」は卑弥呼の墓である可能性が極めて高い。
②虎ヶ岳は「三柱山古墳」(標高148m)の地形を含むものであるかもしれないが、「三柱山古墳」そのものを指す名称ではない。
③「三柱山」の名称は古来から宗像三女神の墓を意味するものと考えられ、安心院町誌(p.48)の遺跡配置図にある「い 三柱山古墳」という名称は不適切(「三女神社古墳」とでも名称変更するのが望ましい)。
源次様は郷土史家として地元の振興に資する立派な活動をされている方のようですので、頭が下がります。当方の研究成果は地元に多大な利益をもたらす可能性があると考えていますので、何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
もしも当方の結論に反論が御座いましたら、この場は不適切とのお考えのようですので、当方のブログにコメントしてお教えください。
以上、よろしくお願いします。
刮目天様
もはや蛇足ですが、繰り返します。
「箱式石棺を複数主体部として持つ古墳」とは申しておりません。「箱式石棺群を墳丘に持つ古墳」です。
現状通りの位置に石棺墓群があったのなら、そのような古墳は類例がありません。調査結果に基づく推論はここまでです。
原位置不明という立場を取って、箱式石棺墓群という調査結果を否定して、発見されている石材が全て繋がって、巨大な石室になるというのは根拠のない想像です。
しかも、その場合はすでに致命的な矛盾が生じています。卑弥呼の墓は「棺あって郭なし」なのです。石室の存在は否定されなければなりません。また時代も後代にずれ込んで、とても弥生時代の墓とは看做せません。ご想像に反する場合も、準ずる場合も、卑弥呼の墓という実像には沿わないことを付記します。
地点の呼称に明確な誤りがあるのはご理解の通りです。
石棺墓群が原位置にあるとすれば古墳であることの否定材料であり、本来丘の上にあったとする根拠はないので古墳である証左とはなりません。
考古学会・史学会の末端ながら、小生は専門家らと市の予算を受けつつ、郷土史研究会を運営し、定期研究会の開催、学芸員の招聘を行い日々研究成果の積み上げと査読を続けています。今年は3回、講師として外部へ史学講演の場を持ちました。
従って想像の積み上げで論を組み立てになる貴下の論理展開とは手法を異にします。
あくまで私が申し上げたいのはこの記事の不適当性であって、貴下の持論の妥当性は私の検討の外にあるものです。ブログへお伺いは致しかねますので何卒ご了承ください。
刮目天です。追加です。
「gooブログ」が今年の11月に閉鎖される予定ですので、新規の記事はすでに「はてなブログ」で作成して、以前の記事も移行しています。ただし、記事の中で「gooブログ」の記事にリンクしている個所は移行しきれていませんので、11月以降はエラーになります。その場合は「はてなブログ」の中で「リンク先」を検索すると出てまいります。よろしくお願いいたします。
「はてなブログ」https://katumoku10.hatenablog.com/
>なおかつ、虎ヶ岳は頂上に自然石が残る祭祀遺跡の様相を呈していますが、それが古墳に転用された例はありません。
おっしゃるとおりです。虎ヶ岳には大きな岩が点在しているようで、一柱謄宮のような磐座祭祀が行われたと考えています。駐車場の立石群によって環状列石も構築されていたのではないかと考えていたのですが、佐田京石から運んだものなのですね。有難うございます。
>また、環状列石を伴う墳丘であったすれば魏志倭人伝の記述にもそぐわないことになります。
魏志倭人伝には卑弥呼の墓について「大作冢 徑百餘歩 狥葬者奴碑百餘人」と書かれているのですが、卑弥呼が葬られてから後に、大国主と台与が訪れて、どこからか大きな岩を運び、祭祀していたと推理しています。文脈から考えて、倭人伝に祭祀のことが具体的に書かれていなくても特に不思議ではないと思います。
虎ヶ岳頂上の鎖と「おおいたの古墳と神社」の件、了解しました。また源次様の御主張は分かりました。どうも有難うございました。
今後の議論は、拙ブログにてお願いいたします。
以上です。
「石棺が複数あっても、そういう例ただ、すでに石棺は壊されています。」は文字がが飛んでしまい意味不明ですので以下の通り訂正します。
「石棺が複数あってもそういう例はあります。ただすでに破壊されているのでそこは分かりません。」です。申し訳ありません。
(つづく)
源次様
刮目天です。お世話になります。
早速お返事ありがとうございます。
>「墳丘上に箱式石棺墓群を伴う例はない」と申し上げております。
墳丘上に複数の箱式石棺墓を伴う古墳の例は存在します。
いくつか例を挙げます。
三成古墳(岡山県笠岡市): この前方後円墳では、後方部と前方部の中央にそれぞれ1基の箱式石棺があり、さらに後方部の墳丘中にも1基、墳丘裾に2基の箱式石棺が確認されています。
鉢の窪3号墳(大分県豊後大野市): この古墳の墳頂には、舟形石棺と箱式石棺の2基の主体部が並置されています。
仲仙寺古墳群(島根県安来市): 仲仙寺支群の9号墳(四隅突出型墳丘墓)では、墳頂部に3つの土壙があり、それぞれに組合木棺が納められていましたが、他に墳丘裾部に3基の箱式石棺があったとされています。
これらの例から、墳丘上に複数の箱式石棺墓が設けられるケースがあることがわかります。特に、弥生時代から古墳時代への移行期や、地域的な埋葬習慣によって、このような形態が見られることがあります。
>さらに原位置が本来別の場所であったとして、虎ヶ岳上にあったという根拠もありません。
根拠は再三述べていますが、また新たなことを教えていただいたので今後よく検討いたします。
>虎ヶ岳上に本来所在したとして、ご自身が主張する巨大箱式石棺様の岩との関係をどう説明されるのでしょうか。
これも一基の箱式石棺、つまり墳頂に納められた卑弥呼の箱式石棺の蓋ではないかと考えていると説明しています。
>虎ヶ岳上に本来所在したとして、ご自身が主張する巨大箱式石棺様の岩との関係をどう説明されるのでしょうか。
このような古墳では副葬品があるのが普通で、通常は重い石板を蓋としています。残念ながらすでに盗掘にあったと考えています。
>径百歩の規模が魏志倭人伝の描写と一致することを虎ヶ岳が卑弥呼の墳墓とする根拠とされておられますが、同書は卑弥呼の墳墓に複数の被葬者があったとは描写しておらず、矛盾します。
当方は、知人から聞いた石棺の部材の量から複数ではないと考えているのです。もしも、卑弥呼ひとりの石棺であればなおさら矛盾などしません。石棺が複数あっても、そういう例ただ、すでに石棺は壊されています。福岡市堂ノ山箱式石棺墓のように一つの石棺内に複数の遺骸を納めたケースもございます。
(つづく)
刮目天様
前略申し上げ、要点を述べさせていただきます。
・箱式石棺墓群について
「墳丘から箱式石棺が出た例はない」とは申し上げておりません。
「墳丘上に箱式石棺墓群を伴う例はない」と申し上げております。
さらに原位置が本来別の場所であったとして、虎ヶ岳上にあったという根拠もありません。
虎ヶ岳上に本来所在したとして、ご自身が主張する巨大箱式石棺様の岩との関係をどう説明されるのでしょうか。
径百歩の規模が魏志倭人伝の描写と一致することを虎ヶ岳が卑弥呼の墳墓とする根拠とされておられますが、同書は卑弥呼の墳墓に複数の被葬者があったとは描写しておらず、矛盾します。
なおかつ、虎ヶ岳は頂上に自然石が残る祭祀遺跡の様相を呈していますが、それが古墳に転用された例はありません。
三女神社境内の三柱石に対応するため虎ヶ岳が古墳であるというお話については、申し訳ございません。因果が成立しているとは思われず、理解ができませんでした。
むしろ、貴下が三柱石がある丘=三柱山であるとご理解されないことに疑問を生じます。
・旅行村駐車場の環状列石
佐田京石から移されて建てられたものであったので、原位置である佐田に戻されました。
虎ヶ岳から移設されたものではありません。
また、環状列石を伴う墳丘であったすれば魏志倭人伝の記述にもそぐわないことになります。
・虎ヶ岳頂上の鎖
松本清張が卑弥呼の墳墓と主張したため、整備を中止して鎖で囲ったものです。
・おおいたの古墳と神社
残念ながら、著者の主眼は三女神社石棺墓群と下市の横穴墓群にあります。
著者は専門知識がなく、考古学の基礎知識が不足した方で、根拠を伴わず展開される内容自体には論評する価値はありません。旅行村にかつて存在した案内版の記載と虎ヶ岳の記述、それから松本清張の推測と地元考古学の受け止めが記述されていましたので引用しました。
いずれにせよ、こちらもご自身でお読みいただきたくお願いします。
ご論説自体への反論は控えます。それはこのサイトの趣旨ではないからです。
再びこちらに記載された丘が古墳として確認された事実はないことと、三柱山という呼称が誤りであることを繰り返し申し上げ、返信といたします。
前回ご紹介いただいたのは安心院町史ではなく1970年発行の「安心院町誌」ですね。国会図書館で閲覧できるようです。松尾則男「おおいたの古墳と神社」東九企画(大分)2004年も近隣の図書館に無いので、近々国会図書館で調査しようと考えているところです。また新しい知見がありましたらご報告いたします。
以上ですが、差し支えなければ拙ブログにお越しいただき、議論していただけると有難いです。どうぞよろしくお願いいたします。
実は大国主は巨石愛好家だったと分かっています。安心院町佐田地区の米神山の裾にある佐田京石は日本一立派な環状列石と言われています。卑弥呼の死後の内戦に勝利したことを祖神に感謝し、国づくりの成功を祈願したのではないかと考えています。
つまり、大国主が佐田川の葦の群生を切り払い水田として豊葦原瑞穂の国にした場所だと推理しています。佐田神社の祭神は武内宿禰・素盞嗚尊・大山祇命ですが、昔は神在月に神々が集まったとされる出雲国二ノ宮佐太大社の主祭神は猿田毘古大神ですが、大国主の分身なのです。安心院の佐田神社も大国主をカモフラージュする祭神になっています。詳細は「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」をご参照ください。
米神山中腹の月の神谷に多数の石棒が揃って一つの場所を指していることが分かりましたので、大国主の父で倭国大乱の英雄日高彦(倭人伝の狗古智卑狗、ムナカタ族を束ねる王の襲名)の終焉の地の菊池川中流域の集落群を見渡す台地上に茶臼塚古墳を発見しています。さらに不思議なことは、この古墳から約80kmの米神山を経由し、さらに約400km北東に父の本拠地で大国主の生誕を記念する石碑を発見しています。このスピリチュアルな直線を霊ラインと呼んでいます。その他にもスサノヲの霊ラインも発見していますので、ご興味があれば「【刮目天の古代史】霊ラインの謎?」へどうぞ。
(つづく)
また「おおいたの古墳と神社」を見ていないので教えて欲しいのですが、この本の冒頭に、大分大学名誉教授神戸輝夫氏の推薦文の中に「古墳と神社の関係を明らかにするもの」との記事をネットで見つけました。ということは虎ヶ岳と三女神社の祭神を結び付けて考えている、つまり著者の松尾則男氏は虎ヶ岳を古墳と見ていたということでしょうか。源次様は『虎ヶ岳の露頭を松本清張は石室ではないかと推測しました。貴下も同じものを石棺の蓋と推測されていますが、同地には石切り場があったことが「おおいたの古墳と神社」などに記載されております』と述べておられます。
私は以前、三柱山古墳の前の広い駐車場の島の中に立石群があったので、直ぐに三柱山古墳の中にあった環状列石を下で再現したのではないかと思い浮かびました。現在撤去されているようで残念です(「卑弥呼の墓は今?」参照)。
(つづく)
次のご認識ですが、「墳丘に箱式石棺墓群を伴う古墳の例はありません」は思い違いです。例えば、古墳時代初頭と考えられる福岡市堂ノ山箱式石棺墓や五世紀初頭の前方後円墳大分市亀塚古墳、久留米市祇園山古墳の墳頂部の中央に長さ約2m、幅約0.9m、深さ約0.9mの箱式石棺は大国主の墓と推理していますが、古墳の墳頂部に箱式石棺の例はかなりあります。ですから「むしろ8群の存在は虎ヶ岳が古墳ではないことを示唆する材料です」とのお考えも間違いということになります。
当方は前回引用した昭和59年3月の調査報告書の文章からは数基の石棺群であったとの伝聞を記載したと分かりますが、実際にあったのは一組分の箱式石棺の部材だったという知人の情報と(第65図にも丸の中に点が1個なのもそれを裏付けるものです)、墳頂部付近に1つの箱式石棺の蓋の可能性がある二・三枚の分厚い石板があったことから三柱山古墳が卑弥呼の墓と現在も考えています。
なぜ、墓の裾にあったかについては造成工事中に偶然発見されたものとしていますが、旅行村の初期の案内図には古墳の墳頂部から下まで長いスライダーが建設されたと分かり、現在スライダー部分は撤去されていますが、土台の基礎部分が露出しているので、その工事中に石棺と知らずに誤って壊したか、石棺の部材を発見して、工事の邪魔になるので裾にまとめて置いたと推理しています。蓋はかなり重いので下まで運べずに、その場に立てて、安全のために鎖と杭で囲ったのだと想像しています。70年代の工事の写真が国土地理院に残っており、南側には石棺が出るような場所があったとは考えにくいということもあります。(つづく)
源次様
刮目天です。また、いろいろといい情報を戴き有難うございます。
早速ですが、源次様が「虎ヶ岳を当方以外三柱山と呼んだ事実はない」とのご認識ですが、これについては繰り返しになりますが、墓の遥拝所とヒカケ横穴の存在などによって、三柱山は日本書紀で宗像三女神とされた卑弥呼の魏志倭人伝に描かれた径百余歩の冢(ちょう、塚)と考えられることを説明しております。
当方は現役時代は理系の研究職でしたので、定年退職後、すでに15年ほどになりますが、謎の古代史解明をライフワークとして、発見的な推論法として知られるアブダクションを用いて科学的に仮説構築に取り組みましたので、当方がはじめて主張するオリジナルの内容が多数あります(考え方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する」参照)。
矢野武夫氏も卑弥呼の墓が一柱謄宮とされていますが、卑弥呼は宗像女神、宇佐神宮の比売大神で宮ノ原の奥城を居城としていたとの認識は当方と同じです。一柱謄宮には三柱山古墳から遺体を動かしたのかははっきりしませんが、大国主と台与が卑弥呼を改葬して鎮魂祭祀を行った場所であろうと推理しています。
妻垣神社がスサノヲのオロチ退治の後にイナダヒメと八重垣神社に逃げて、歌った日本最初の歌謡に因む社名なのです。ヤマタノオロチは出雲国風土記にありませんし、スサノヲはすでに奴国宮廷楽師らの反乱で殺されていますので史実を誤魔化すためのものなのです。
そして一柱謄宮を日本書紀では神武東征神話でイワレヒコが母玉依姫の墓参のために最初に立ち寄った場所としており、ウサツヒコとウサツヒメの歓待を受けたとしています。そこで東征に従った藤原氏の遠祖天種子命がヒメを娶る許可をいただいたと、創作した祖神を称えるホラを吹いています(ウサツヒコは大国主、ウサツヒメは13歳で女王にされた台与なのです、詳細は「ヤマタノオロチの正体もか?」参照)。初代神武天皇の話は、初代ヤマトの祭祀王応神天皇の史実を隠すために創作したものなのです。それは応神天皇崩御後の皇位争いを誤魔化すためにも使われています。
(つづく)
付記
貴下の持論に関してもちろん目を通しましたが、邪馬台国の所在、卑弥呼の墓の所在を云々する以前に、①当該の丘の名称が誤りであること。また②虎ヶ岳は古墳とは確認されていないことが私の指摘です
これらにつき私が把握していない事実があればご教示ください
刮目天様
ご期待に添えず誠に申し訳ございませんが、当該の資料は私の著作物ではありませんのでこちらに画像をアップロードすることはできません
また、そのような画像掲示は当サイトの趣旨に反すると考えます
こちらの目的は各自の自説を主張・検証することになく、客観的事実を訪問者と研究者に紹介するにある筈です
いずれの資料も所蔵館へ足を運ばなくても、国会図書館サーチで検索できますので、日本全国所在地を問わず入手可能な資料です。ご自身で調査される労をお取りください
まず、確定している事実を申し上げます
このページで取り上げられている丘はこれまで、貴下以外から三柱山と呼称された事実はありません。名称は虎ヶ岳です
次に、発掘調査報告書に「第8群」として記載されている喫茶店裏に露出している箱式石棺墓群の存在を古墳の遺物とされていますが、墳丘に箱式石棺墓群を伴う古墳の例はありません。複数主体部の例を引いても位置が特異に過ぎます。むしろ8群の存在は虎ヶ岳が古墳ではないことを示唆する材料です
また、第8群を記した発掘調査報告書を意図的にミスリードされているのかもしれませんが、周辺の丘で遺物の存在が疑われる=古墳や石棺墓の存在が確認されている丘はきちんと図示されていますが、それらに並ぶ虎ヶ岳にはその記載がありません。専門家の目から見て虎ヶ岳に遺物は確認されていないのです
虎ヶ岳の露頭を松本清張は石室ではないかと推測しました。貴下も同じものを石棺の蓋と推測されていますが、同地には石切り場があったことが「おおいたの古墳と神社」などに記載されております
ここまでで、残念ながら確認されているすべての事項において、三柱山という呼称も適当でなく、古墳であるという事実も確認されていないわけです
以上は反論ではありません。事実の列挙です
ここは各々の自説を展開する場所ではありませんし、また討論する場所でもありません
学術的に確認されていない場所を古墳として記載するのは適当でなく、またその名称すら別の場所と混同していることを放置し、いたずらに誤解を招く行いは適切ではありません
魏志倭人伝の正始八年(247年)の卑弥呼の死の前後の記事からごく短期間に造成された「径百余歩の冢(直径約150mの円形墳墓)」に合致するものです。また、その西側が、奴婢百余人を殉葬したことを示唆する「血野」という地名となっており、これも合致します。さらに、墓の南側約400mの深見川の河原に同名の三女神社があり、三女神の石塔が三基、三柱山古墳に正対して置かれていますので、卑弥呼の墓の遥拝所だと分かりました。しかし、面白いことに、そこから古墳を直接目視できないように土を人工的に盛り上げてあり、さらにそこに「ヒカケ横穴群」とされた日食のために殺されたことを示唆する天岩戸を連想する名称の横穴があります。その入り口に馬頭観音の石像が置かれていますので、卑弥呼の史実を知る地元の方が建立されたものと考えています。
さらに、この神社の西側に摂社が二つあり、神額が八束神社と金毘羅宮とあります。金毘羅宮の祭神は大物主ですので、宗像明神とされた神話の大国主(豊岡市久久神社祭神久々遅命、魏志倭人伝の狗古智卑狗)のことです。ですから八束神社の祭神は出雲国風土記の冒頭の意宇郡にある国引き神話の八束水臣津野神で、日本全国のムナカタ海人族を束ねる大国主の祖父にあたる実在人物の八束命(略称、記紀神話で海神豊玉彦命であり瓊瓊杵尊とされたムナカタ海人族を束ねた奴国王スサノヲの子孫の出雲王)と突き止めています。
これらの情報から卑弥呼は日本書紀で宗像三女神として隠されたムナカタ海人族和邇氏の姫巫女だということが分かりました。天理市和邇坐赤阪比古神社の祭神が市杵島姫命なのです。奥城古墳の被葬者が卑弥呼の父赤坂比古と推定しています。ですから、八束命の姫を娶った赤坂比古の娘市杵島姫命が卑弥呼とされ、大国主久々遅彦とは「いとこ」の関係になります。4世紀に和邇氏は天皇の妃を出し、有力豪族として全国に展開していますので、宗像神社、厳島神社、そして弁財天宮で最も多くの寺社で祀られています。ですから、三柱山古墳は卑弥呼の墓の最有力候補と考えています。詳しくは【刮目天の古代】卑弥呼の謎!などをご参照ください。
どうか、冒頭でお願いした資料開示の件、これから参考にさせていただきたいので、ご面倒をおかけして恐縮で御座いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
源次様
お世話になります。安心院町史に記載された三柱山について丁寧にご説明頂き感謝いたします。この件についてさらに検討したいので、よろしければ、安心院町史の該当記事や図版など関係資料を古墳マップにご開示いただけないでしょうか。
手元にある「宮ノ原・三柱山所在遺跡の調査報告書」(安心院町教育委員会昭和59年3月31日)には第8石棺群と記載されていますが(第65図、p.91)、当方が三柱山古墳と主張している地形の南麓に石棺一つ分の部材が固めて置かれていたと知人から聞いています。先日確認しようとしたのですが、見当たらなかったのでガッカリし、宇佐市教育委員会に保全していただくようお願いしております。すでに、墳頂付近に石棺の蓋と考えられる分厚い石板が複数枚あることは確認しています。ですから、報告書に記載されたように「第8石棺群は、現在喫茶「独歩」の裏に露出しているもので、造成中にも石棺が出土したと聞く。数基の石棺群であったようである。」(p.94)とあることから、この古墳からなにも出土していないという源次様のご主張は理解できません。
奈良文化財研究所に登録された「三柱古墳」の名称は、登録された時に、三女神社の在る小字名「三柱」により命名されたようで、位置を示す図はありませんので、当方が勝手に「三柱山古墳」と命名しています。というますのも、古墳は〇〇山と古くから呼ばれるケースが多く、この場所は宗像三女神の墓という意味で古くからその代名詞となっていたと考えるからです。
宮ノ原遺跡は三女神社の北側の弥生時代から古墳時代初期の集落です。日本書紀で三女神として隠された卑弥呼の侍女(奴婢)や警護する兵士のおよそ数百名居住の集落だったと考えています。宮ノ原は古くは奥城(おくじょう)と呼ばれていたと、ご存じかと思いますが、安心院町の町長を歴任された元県会議員矢野武夫氏の「卑弥呼の墓発見」(安心院町文化連盟 1976年)で、妻垣神社奥宮の一柱謄宮を卑弥呼の墓とされています。その中で、「卑弥呼の住居跡は、宇佐の奥の院、安心院谷の宮の原の奥城といわれる処であったともいわれている。」(p.115)とあります。ということで第8石棺群が出土した古墳は、卑弥呼の死の直後に葬られた墓であると推理していたからです。
(つづく)
刮目天様
松本清張がかつてその丘を卑弥呼の陵としました。おまけに山頂には石室にも見える石があります。ですからお気持ちはわかるのですが…。
現在宇佐市の史跡地図に仰る位置は史跡としてマークがありません。また旧資料として確認できる安心院町史にも三柱山古墳は別の位置に記載されています。
また、そもそも提示なさったリンク先の発掘調査報告書をお読みになられたことはあるでしょうか。同発掘調査報告書にはその丘について、なんら遺跡としても遺物の検出地点としても記載がありません。何より、「三柱」の小字はその地点ではないからです。
「三柱山古墳」として安心院町史に記載のある地点は奥城古墳(奥城石棺群)の南東です。
また同資料には「三女神社台地」と同地点に「三柱山遺跡」の記載があります。即ち三柱山とは三女神社の丘を指すのです。
なお同遺跡は現在の遺跡地図では211174番の宮野原遺跡として登録されています。内容は集落・墳墓となっており、安心院町史記載で、当時古墳とは見なされていた三柱山、不動山、ヒカケ、倉谷山の各石棺群を含む遺跡ですが、旅行村の敷地、およびご主張の丘は含まれていません。
即ち出土品の関連からも文献からも古墳とは確認されていないのです。
そもそも松本清張が古墳と主張した時点で、この丘は「虎ヶ岳」と呼ばれていることが明白です。三柱山とお呼びになって、古墳と主張されているのはご自身のみというのが事実です。
このページ自体の削除も検討されるべき状況と考えます。
源次様
刮目天です。お返事が遅くなって恐縮です。
この古墳は奈良文化財研究所「全国文化財総覧」に下記のとおり記載されています。ただし、古墳名が三柱古墳とあり、これは所在の安心院町下毛字三柱山が間違って三柱と記載されていたためのようですので三柱山古墳が正しいと考えられます。ちなみに調査報告書銘はCiNii に「安心院宮ノ原遺跡 : 大分県宇佐郡安心院町下毛宮ノ原・三柱山所在遺跡の調査報告書」とありますのでご確認ください。https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN14759417
記
日本全国文化財番号 (JC番号:JCNo) : 231875
大分県 宇佐市 三柱古墳
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/cultural-property/231875
[RecNo:184063] 三柱古墳
所在 : 大分県宇佐市安心院町下毛字三柱
市町村 : 宇佐市 ( 44211 )
種別 :
主な時代 :
遺構概要 : 古墳
遺物概要 :
発掘概要 :
その他概要 : 旧、宇佐郡安心院町。 〈全国遺跡地図_位置〉b2/〈全国遺跡地図_旧番号〉103/〈全国遺跡地図_県番号〉 /<全国遺跡地図番号> 6-14
石棺墓群が近隣から検出されているに過ぎず、古墳として確認されているものではありません。
出土遺物も遺構もありません。即ち地形からの推定に過ぎません。